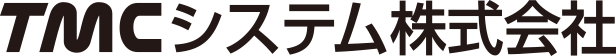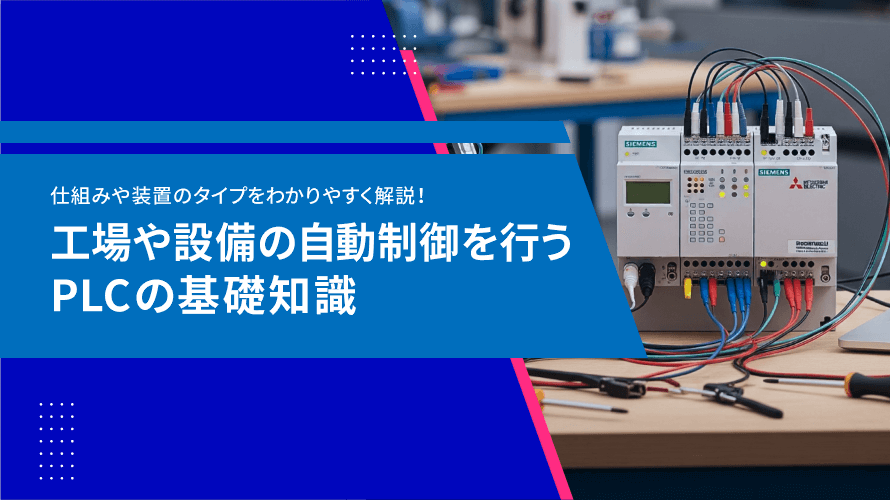衝撃試験とは?種類・規格から最適な選び方まで、基本をわかりやすく解説
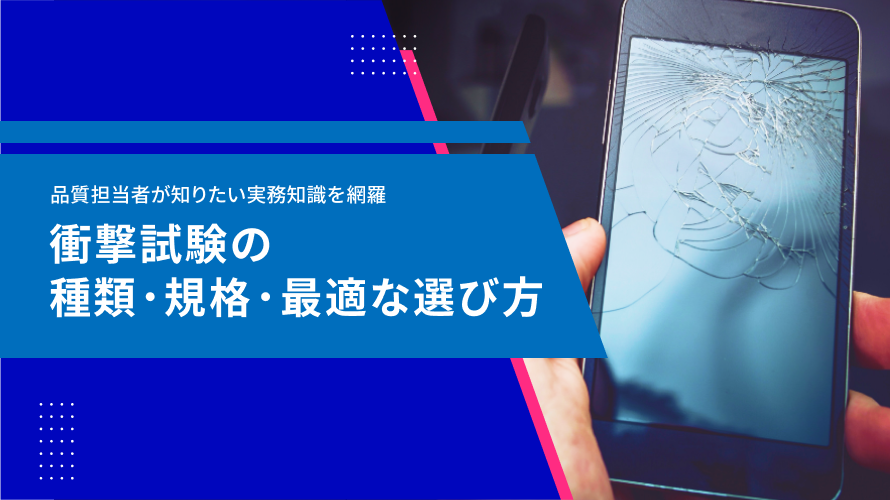
目次
なぜ衝撃試験が重要なのか?静的試験では見抜けない「隠れた弱点」
「静的試験の強度はクリアしたはずなのに、なぜか市場で破損トラブルが起きてしまう…」
製造業の品質保証や製品開発の現場では、このような課題に直面することがあります。その原因は、製品が実際に受ける『衝撃』への耐性を見過ごしていることかもしれません。衝撃試験とは、製品や材料に対して、意図的に衝撃を加えることで、その衝撃に対する強さ(靭性)や、もろさ(脆性)を評価するための重要な試験です。
衝撃で評価する「靭性」と「脆性」とは?
同じ強度の材料でも、衝撃を受けたときの「壊れ方」は大きく異なります。
| 性質 | 衝撃を受けたときの壊れ方 | 代表例 |
|---|---|---|
| 靭性 (じんせい) |
粘り強く抵抗し、徐々に変形しながら壊れる | 軟鋼、一部のプラスチック |
| 脆性 (ぜいせい) |
急激に破断し、変形せずに突然割れる | ガラス、セラミックス、低温の金属 |
衝撃試験の主な目的は、製品や材料に落下・衝突といった瞬間的な衝撃力を加えることで、その材料がどのように「壊れるか」という性質を評価することです。これにより、実使用環境で起こりうる破壊リスクを事前に把握し、製品の安全性と信頼性を確保することが可能になります。静的試験だけでは分からない、こうした材料の「壊れ方の性質」を明らかにすることが、衝撃試験の重要な役割です。
衝撃試験と振動試験はどう使い分ける?
衝撃試験と振動試験は、どちらも製品の耐久性を評価する重要な動的試験ですが、その目的は全く異なります。
例えるなら、衝撃試験が「ボクシングのストレートパンチ」に耐えられるかを調べるのに対し、振動試験は「長時間のマッサージチェア」のような揺れに耐えられるかを調べる、というイメージです。
| 比較項目 | 衝撃試験 | 振動試験 |
|---|---|---|
| 力の種類 | 落下・衝突のような「瞬間的な力」(ドン!) | 輸送・稼働中の揺れのような「継続的な力」(ガタガタ…) |
| 評価する事象 | 一度の大きな衝撃で壊れないか | 長時間の揺れで疲労したり、緩んだりしないか |
| 身近な例 | スマートフォンの落下 | 洗濯機の脱水中の揺れ |
このように、瞬間的な衝撃への耐性を深く掘り下げるのが、本記事で解説する「衝撃試験」です。 一方、より広い概念である振動試験の全体像については、振動試験の基礎知識 〜製品の信頼性を確保するために必要な試験とは〜で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
3ステップでわかる!自社に最適な衝撃試験の選び方
衝撃試験にはいくつかの種類があり、「どの試験方法が自社の目的に適しているのか分からない」という方も少なくありません。以下のシンプルな3ステップで、自社の目的に合った最適な試験方法を迷わず選定できます。
ステップ1:評価対象は「材料」か「製品」か?
まず、評価したい対象が、規格化された「試験片」なのか、実際の「製品」なのかを明確にします。
- A. 材料の基本特性を知りたい(試験片での評価)
目的: 研究開発、材料の受け入れ検査など
対象: 金属、プラスチックなどの材料から切り出した規格試験片
└─▼ 【ステップ2へ】 - B. 製品そのものの強度を知りたい(完成品での評価)
目的: 完成品の品質保証、実使用環境での耐久性確認
対象: 最終製品、部品、複合材料、板・フィルム材
└─→ ★ 推奨試験:落錘・落球衝撃試験、製品落下試験
ステップ2:材料の種類は「金属」か「プラスチック」か?
(ステップ1でAを選んだ場合)
次に、試験片の材料の種類によって、主な試験方法を絞り込みます。
- 金属材料 → シャルピー衝撃試験
- プラスチック(樹脂)材料 → アイゾット衝撃試験
これらの試験は、それぞれの材料に特化したものではありませんが、実務で多く用いられる組み合わせです。詳細は後の章で解説します。
ステップ3:準拠すべき規格を確認する
最後に、適用すべき規格の有無を確認します。これは最終的な決定要因となります。
- 規格の指定がある場合 → 材料や目的に関わらず、規格で指定された試験方法を最優先します。
- 規格の指定がない場合 → ステップ1、 2の結果に基づき選択できます。
主要な衝撃試験で何がわかるのか?
前の章で、自社に合った基本的な試験方法がおわかりになったかと思いますが、ここでは、それらの試験で具体的に何がわかるのかを深掘りすると共に、さらに高度な分析を可能にする計装化衝撃試験についても解説します。
シャルピー衝撃試験 - 主に金属の低温でのもろさを評価
試験片の両端を支え、中央をハンマーで叩く試験です。金属材料の評価に用いられることが多く、特に「延性-脆性遷移温度」(ある温度を境に急激にもろくなる性質)の評価に不可欠です。寒冷地で使われる金属部品の品質保証などで重要な役割を果たします。
アイゾット衝撃試験 - 主にプラスチック製品の耐衝撃性を評価
試験片の片側を固定し、ハンマーで叩く試験で、プラスチック材料の評価に多用されます。プラスチックは温度や湿度の影響を受けやすいため、試験前の「コンディショニング(温湿度調整)」が結果を大きく左右します。
落錘・落球衝撃試験、製品落下試験 - 製品そのものの強度を評価
これらの試験は、局所的な衝撃への耐性を評価するのか、製品全体の総合的な耐性を評価するのかという目的によって内容が異なります 。
落錘・落球衝撃試験
目的: 特定の部位に衝撃を与え、局所的な強度を評価する
内容: 決められた高さから重り(錘や球)を落下させ、試験片や製品に衝突させる
製品落下試験
目的: 製品全体の総合的な耐衝撃性を評価する
内容: 製品そのものをさまざまな姿勢(面、角、辺など)で落下させる
計装化衝撃試験 - 破壊の「質」まで詳細に解析
この試験の最大の特徴は、衝撃中の「荷重」と「時間」のデータを連続的に記録できる点です。これにより、単なる「吸収エネルギーの総量」だけでなく、下記のようなより詳細な情報が得られます。
- 破壊開始エネルギー: 亀裂が「発生する」までの粘り強さ
- 破壊伝播エネルギー: 亀裂が「広がっていく」過程の粘り強さ
これにより、「亀裂は入りにくいが、一度入ると一気に壊れる材料」と「亀裂は入りやすいが、完全に壊れるまで粘る材料」といった、破壊の「質」の違いまで定量的に評価できます。
衝撃試験の不具合分析と対策
試験の実施後、得られたデータを次の製品改善に活かしてこそ、試験の価値は最大化されます。ここでは、報告書を読み解き、具体的な改善アクションに繋げるための2つのパターンを見ていきましょう。
パターン1:吸収エネルギーが目標値に届かなかった場合
考えられる原因:
- 材料自体の靭性不足
- 成形時のウェルドライン(樹脂が合流する部分にできる脆弱な線)など、工程に起因する強度低下
改善アクションのヒント:
- 【材料】 より靭性の高いグレードの材料に変更、または改質剤を添加する。
- 【設計】 部品の肉厚を増したり、リブ(補強)を追加したりして形状で強度を補う。
- 【工程】 ウェルドラインの影響を最小化するよう金型設計や射出条件を見直す。
パターン2:低温になると、著しく脆くなる場合
考えられる原因:
- 材料の延性-脆性遷移温度が、想定される使用環境よりも高い。
改善アクションのヒント:
- 【材料】 より低温靭性に優れた材料(遷移温度が低い材料)を選定し直す。
- 【設計】 ヒーターを追加するなど、部品が極低温に直接晒されないような対策を検討する。
- 【詳細分析】 計装化試験で破壊のメカニズムを詳細に分析し、材料開発にフィードバックする。
「外注」と「内製化」、どちらを選ぶべきか?
試験の実施を検討する際、「外部の試験機関に委託するか、自社で設備を導入するか」は重要な判断ポイントです。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、判断の目安を解説します。
【外部委託】
- メリット: 初期投資が不要で、信頼性の高いデータが得られる。
- デメリット: 時間がかかり、頻度が多いと割高になります。ノウハウが蓄積しにくい。
【内製化】
- メリット: 開発スピードが向上し、社内にノウハウが蓄積できる。長期的にはコストを削減できる。
- デメリット: 高額な初期投資と、設置スペースや運用コストが必要。
| 比較項目 | 外部委託 | 内製化 |
|---|---|---|
| 初期コスト | ◎ 低い(不要) | ✕ 高い |
| 運用コスト | △ 試験の都度発生(変動費) | 〇 長期的には割安(固定費) |
| 開発スピード | △ 遅い(外部との調整) | ◎ 速い(いつでも実施可能) |
| 技術ノウハウ | ✕ 外部に依存 | ◎ 社内に蓄積される |
| おすすめの企業 | ・試験頻度が少ない企業 ・多様な規格への対応が必要な企業 |
・試験頻度が多い企業 ・開発スピードを最優先する企業 |
衝撃試験に関するご相談は、TMCシステムへ
今回は衝撃試験についての基礎知識から、最適な試験の選び方、そして結果の解釈と製品改善への活用方法までを解説しました。しかし、製品の特性や開発の目的は多岐にわたり、ご紹介した内容はあくまで一例に過ぎません。
当社には、オーダーメイドの製品落下試験機や重り落下試験機(いずれも力計測機能付き)の開発実績がございます。通常の衝撃試験では、破壊したかどうか、どの程度のエネルギーを吸収したかという結果しか得られませんが、力計測機能があれば、衝撃中の「力」と「時間」のデータを連続的に記録できます。これにより、単なる破損の有無だけでなく、製品がどのように壊れていったのか、その破壊の質まで詳細に解析することが可能になります。
自社製品に最適な試験方法がわからない、特定の規格に準拠した試験をしたいなど、衝撃試験に関する個別のお困りごとはございませんか?
TMCシステムでは、お客様の製品特性や評価目的に合わせた最適な衝撃試験ソリューションをご提案させていただき、要件のヒアリングから装置の設計・製作、導入後のサポートまで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。